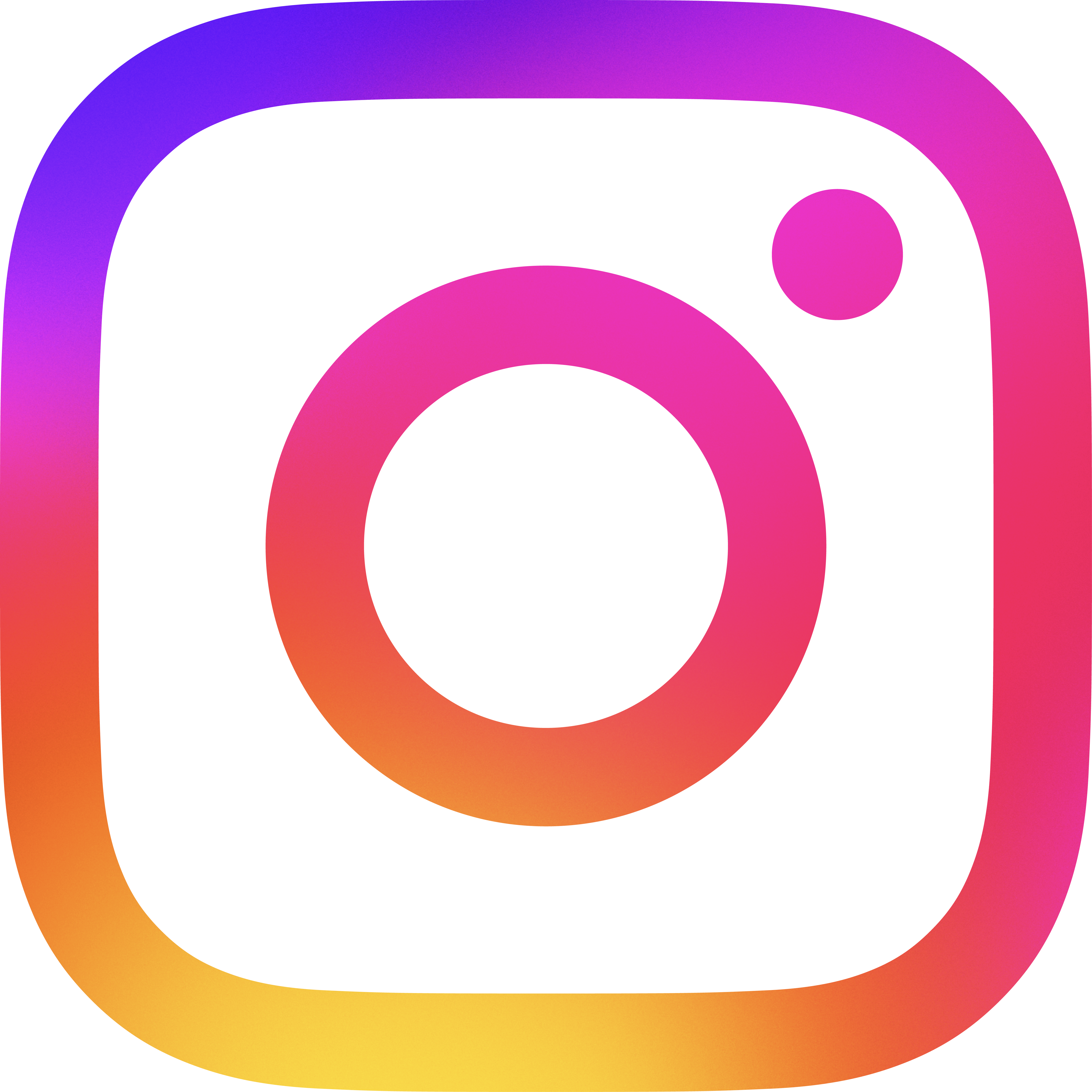お知らせ
成田幼稚園ニュース
-
New
2026年2月18日 -
新入園児一日入園のつどい🌺😃😃😃🎵
- 2026年2月17日
-
今日はプレ保育😃😃😃
- 2026年2月16日
-
生活発表会😃😃😃
- 2026年2月13日
-
🌺あしたは、ワクワクドキドキの生活発表会~🎵
- 2026年2月2日
-
きょうは園の節分会👹🥜
- 2026年1月23日
-
きょうは プレ保育dayです🎵
- 2026年1月21日
-
はじめての英語村🎵Good job!
- 2026年1月20日
-
きょうもげんき😃😃😃
- 2026年1月19日
-
言えるよ!できるよ!🌺
- 2026年1月16日
-
今日は避難訓練をしました🚒
当園について
成田幼稚園の教育方針

豊かな自然環境・楽しいあそびのなか、
生きる力・心の教育に取り組んでおります。
成田幼稚園は1951年創立の歴史ある幼稚園です。
大阪・寝屋川市で長く地元のみなさまと共に、たくさんの子どもたちを育てて参りました。
アクセス
学校法人 成田山学園 成田幼稚園
〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町10番8号